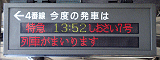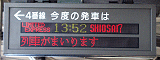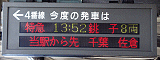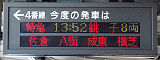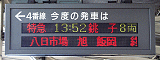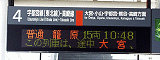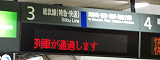| 2000/5/5(金) 公開 |
錦糸町駅の特急・快速ホームには、N'EXと回送電車以外の全列車が停車する。地下区間で導入されているATCと地上区間で使われているATS-Pの境界になっているため、電車側の切り替え作業が必要になる。N'EXも、停車こそしないものの減速して通過する。 |
 3番線に到着する特急しおさい (錦糸町駅、2000/4 撮影) |
特急しおさいの案内
錦糸町駅の電光掲示板には「 種別 88:88 行 先 88両」という書式で電車・列車の案内が表示されている。これは、特急列車より普通の(?)快速電車のほうが圧倒的に本数が多く、中央線の特急停車駅で見られるように列車名の表示領域を確保するほどではないからである。
そのため、特急の場合、例えば「しおさい7号」という列車名は、「銚 子」「CHOSHI」「しおさい7号」「SHIOSAI 7」という具合で、行き先と交互に表示される。限られた表示領域で、うまく列車名を案内する工夫といえよう。 錦糸町駅で見られる特急しおさいの停車駅スクロールは独特である。一般的な「(←)この列車は、○ ○ 、… ○ ○ の順に停車致します。」という表示ではない。これは、総武線(快速)用の中央装置が稼動していないため、駅で独自に設定しているからであると思われる。ATOSの全線導入後は、一般的なスクロールに変更される可能性もある。 写真の通り、「(←)当駅から先 千葉 佐倉 八街 成東 横芝 八日市場 旭 飯岡 終点、 銚子 の順に停車致します。」という全文が赤で表示される。特急だから赤、ということかも知れないが、かなり強烈だ。 ATOSの一般的なスクロール表示では、地の文(?)が緑で駅名が橙、というのが標準になっている。比べると、赤一色より非常に見やすいことがわかる。また、橙色は赤+緑で表現されているので、赤または緑の単色より明るい。特定の部分を強調したい時、紙の上では赤を使うが、電光掲示板では赤よりも橙のほうが、強調表示に向いた色であるといえる。 |
南北改札口にも電光掲示板
総武線の快速停車駅でコンコースへの電光掲示板設置が行なわれたが、錦糸町駅でも北口・南口それぞれに新設された。写真は、上が南口、下が北口の電光掲示板を撮影したものである。 南口には通路の中央や自動改札の間にも柱があるなど、スペースが極めて限られている。そのため、電光掲示板も横1列には並べられなかったようだ。電光掲示板は、本体左右の溝に支柱を固定して設置されるが、使う支柱を長いものにすれば二段重ねにもできるとは、うまくできているものだ。 北口は、すぐ外に出られるほか、南口より広くて開放的だ。電光掲示板は、南口とは違って改札の中に設置されている。 |
  (錦糸町駅、2000/4 撮影) |
北口電光掲示板のその後
上の写真と見比べて欲しい。「2」と「3」の間の空間に、後から電灯つき看板が挟まれているのがわかる。この看板には、JRマークとともに「北口」「NORTH ENTRANCE」「ご利用ありがとうございます」などと書かれている。よく自動改札機の上部にある看板のようなデザインだ。 2枚目の写真は、同じ電光掲示板を背面から撮影している。この電光掲示板は片面のみが表示面になっていて、裏面(=非表示面)はグレーの平らなカバーが取り付けてある。設置当初は看板もなく、背面もグレーのままだった。ところが、4月下旬になって「出口案内」に早変わりした。 3枚目の写真でわかる通り、この「出口案内」はステッカー状になっている。それが、電光掲示板の裏に貼りつけられているわけだ。別に設置するのではなく電光掲示板の裏面を活用するとは、実に合理的である。設置当初、両面とも表示面になっていれば乗り換え時にも見られて良いのではないか、と思ったが、このような「出口案内」がセットになるとは思っても見なかった。 |
   (錦糸町駅、2000/5 撮影) |
コンコースで「列車が通過します」
錦糸町では、なぜか、コンコースの電光掲示板に「列車が通過します」という点滅表示が出る。この表示が点滅している間、コンコースではその番線の電車が全く案内されないことになる。「電車がまいります」や「次は ○ ○ に停車致します。」の表示はホームでしか出ないため、何らかの設定ミスではないかと思われる。 |
関連ページ
・ 導入済み線区
→ 中央線(各駅停車)
→ 総武線(各駅停車)
→ 総武線(快速)
・ トピックス
→ 総武線快速停車駅コンコースの電光掲示板
→ 蘇我駅の電光掲示板交換とその背景
・ フォーラム
→ 【南武線】武蔵中原駅でATOS使用開始、中原電車区にかかる手扱いのため先行か
→ 【横浜線】橋本駅でATOS使用開始、相模線指令の習熟のため先行か
→ 【蘇我駅】千葉駅・京葉臨海鉄道にかかる手扱い継続か
→ 「ホーム系」と「改札系」の違いと軌道回路