
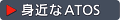
JR東日本の「東京圏輸送管理システム(ATOS)」は、最新の技術で列車運行を自動化する、国内最大の列車運行システムです。東京から半径100kmの円内を「東京圏」と定義し、その圏内を走る19線区を対象に、1993年から導入が進められています。
ここでは、ATOSの全体像や開発の背景を踏まえ、ATOSが持つ各機能を見ていきます。
基礎知識
そもそもATOSとはどんなシステムなのでしょうか。運行管理の歴史をひも解きながら、最新のシステムの実像に迫ります。
→ 概要と機能
→ 旅客案内と運行管理
→ 運行管理の変遷
旅客案内
ATOSに連動した旅客案内についてご紹介します。
ATOSに連動した電光掲示板(LED発車標)では、ATOSによってリアルタイムに把握される運行状況に合わせ、常に適切な案内が行われます。また、ATOSの導入とともに広範囲の駅で整備が進められています。
→ 外観と機能
→ 設置形態
→ 基本的な表示
→ 変則的な表示
→ 遅延時の表示
→ 各種案内の表示
ATOSに連動した自動案内放送では、ATOSによってリアルタイムに把握される運行状況に合わせ、常に適切な案内が行われます。
→ アウトライン
→ 実例1(基本的な放送)
→ 実例2(その他の放送)
→ 検証
運行管理
ATOSによる運行管理に特有の事がらや機器についてご紹介します。
ダイヤが乱れたときの運転整理や一定間隔での運転に威力を発揮するのが出発時機表示器。定時運行を最優先してきた従来の常識を覆す柔軟な運行が可能になり、利便性や快適性の向上が期待できます。
→ 外観と機能
→ 設置形態
→ 表示
|