
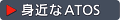
→ 旅客案内と運行管理
一見すると利用客とは関係のなさそうな部分が、実は利便性や快適性に大きく関係していたりします。目立たない変化でありながら、実は鉄道のあり方が根本から変わりつつあるということもあります。ここでは、旅客案内と運行管理の関係をご紹介します。
自動旅客案内と運行管理の関係
例えば、電光掲示板に表示させる情報はどうやって用意するのだろうか。
ポイントのある駅では元来、ポイントを切り替えるためにダイヤの情報が必要である。これは書式を変えることで、電光掲示板の表示にも使える。一方、ポイントのない駅では、必ずしもダイヤの情報を持っている必要がないため、電光掲示板のためだけに情報を用意する必要がある。
このように、駅で自動旅客案内を実施するには、単に電光掲示板を設置するだけでは済まない。そのため、ともすれば自動旅客案内はポイント制御の「おまけ」的な位置づけをされがちで、ATOSが導入される前には、ポイントのある駅だけに電光掲示板が設置されていることが多かった。
ATOSと自動旅客案内の関係
ATOSが導入されると、対象線区の全駅にダイヤの情報が届くため、電光掲示板の設置がしやすくなった。というより、これはATOSの開発に際して自動旅客案内の再評価が行なわれた結果といえる。
ATOSのコンセプトとして、「利用客への迅速・正確な情報提供の実現」が挙げられている。ポイントの有無に関わらず、駅には自動旅客案内が必要だ、という考え方への転換が行なわれたわけである。
ようやく自動旅客案内が運行管理上の「おまけ」から「必要不可欠な機能」に昇格したわけである。
余談:「○○駅にATOSが入る」?
インターネット上では、駅の電光掲示板を指して「ATOS」と表現している例が少なくない。また、自動案内放送を「ATOS放送」と表現するのも定着している。たいしたことではないが、これらの表現はあまり正確ではない。
これらは、当該線区へのATOSの導入に際して整備されているだけで、電光掲示板や自動案内放送を導入するためにATOSが導入されているわけではない。
また、ATOSが導入される線区以外では自動案内放送のタイプも異なるのが普通である。従って、ATOSが導入される予定のない線区の駅で同様の自動案内放送が使用されることをやみくもに期待しても無駄である。
ATOSにおける運行管理のパラダイムシフト
これまでは、いわば「職人芸」ともいうべき熟練の腕に頼った運行管理が行なわれていた。ただ、「職人芸」は人間の手によるものである以上、絶対的な限界がある。また、少子化や人員削減のあおりで技能を継承するのも難しくなってきている。
ATOSでは、一時的に質が落ちるとしても、将来のために自動化の道を探っていく、という方針が取られている。
また、運行管理上の指揮命令系統のトップは指令室であるが、東京圏の過密線区においては実際には駅の進路制御のほうが大変であり、むしろ「○○駅、入れますか?」というスタンスにならざるを得なかった面がある。
ATOSにおいては進路制御は自動化され、ほんの数人の指令員がマウスでダイヤを変更するだけで、必要な変更がすべて自動で行なわれる。指令の方針次第で運行管理ができるようになったわけである。運行管理の重点が、駅の進路制御から指令室へと移行したということである。
とはいえ、現状ではATOSにダイヤ自動回復の機能はなく、指令員のスキルに大きく依存する状態になっている。5分程度であれば従来よりスムーズにダイヤが回復できるが、30分以上の遅れが出るような時には大変きつい状況になることが想像できる。
ダイヤを自動回復する機能は現在、京葉線で実用化に向けた試験が行なわれている。その成果がATOSにも反映されれば、現状が改善される可能性が高い。
将来的には、いつも異なる需要に最適化して電車を運行できるよう、ダイヤをリアルタイム生成するような時代が到来するかも知れない。私たちが数十年後にも時刻表を見ながら電車に乗っているかどうかはわからない。ATOSには、そのような次世代への渡し舟としての役割が期待される。
利用客にとってのメリット
利用客にとってのATOSのメリットは、下記の点に集約される。
・ ポイントのない駅でも自動旅客案内が行なわれる。
いわゆる「何の変哲もない駅」でも、当たり前のように電光掲示板や自動案内放送による案内を受けることができる。特に電光掲示板については、大規模駅のシンボル的存在から、とても身近な存在へと変貌した。
・ 常に最新の情報が提供される。
電車の発車時刻などはもちろん、他の線区の遅延情報も電光掲示板を通して入手することができる。また、ATOSによる集約の副産物として、同じ情報がインターネットや携帯電話などでも同時に提供されるようになった。
・ 電車が遅れにくくなる。
都心の線区では、発車時刻よりも列車間隔を重視した運行管理が行なわれ、電車の遅れを意識しなくて済む場合も多くなった。他線区からの乗り入れ電車が遅れても他の電車に遅れが波及しにくくなった。
関連ページ
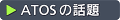
・ フォーラム
→ 「コムトラックph-2」(1972〜1975年)に見る「旅客案内の機械化・自動化」
→ 直通運転に欠かせないATSとCTC:進路制御と列車番号の関係を探る
→ 行先や発車時刻を自動で案内するしくみ(「放送文選択コード」)
→ 空港アクセス列車と「東洋メディアリンクス」(1991〜1999年)
→ ATOSの旅客案内装置が実現したこと、しなかったこと
→ 「連動駅」と「非連動駅」
→ 「表定速度」と「ヘラクレス」(2015年)
→ 「時隔曲線」と「アーラン分布」(1980年7月)
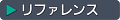
・ 鉄道システム
|