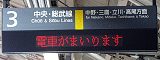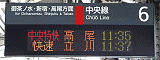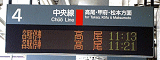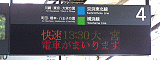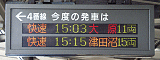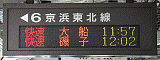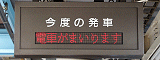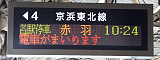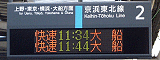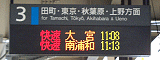| 2005/8/12(金) 更新 |
同一のホームに複数の種別の電車が停車する場合、桁数が多めのものにされることが多い。 特急が停まるホームでは、「特急スーパーあずさ11号 松 本 17:32」などと列車名も表示するため、さらに桁数が多い。ただし、最近は行き先・両数と列車名・号数を交互に表示させる方式が広まりつつある。この方式は総武線の錦糸町や船橋で最初に使われ、現在は秋葉原などでも使われている。今後、特急列車や愛称つき快速の多い路線を中心に、交互表示がスタンダードになっていくのではないかと思われる。 |
ホーム用では全角で8字、10字、12字が標準的である。一部にはかなり大型のものもあり、14字、18字のものも見られる。
一部では24ドットタイプも
表示桁数とは別に、ドット数の違う電光掲示板も存在する。横浜駅では、ATOS線区で一般的な電光掲示板と同じデザインでありながら、LEDマトリックスが24ドットという変わった電光掲示板が使われている。 |
おなじみの「電車がまいります」も明朝体で表示される。JR東日本の新幹線ホームで使われている高品位な電光掲示板の在来線バージョン、といった趣きだ。東京駅でも、コンコースにある東海道線の電光掲示板が24ドットタイプである。
ただし、24ドットすなわち「美しい」とは限らない。16ドットに比べ書体のセンスが問われるため、かえって難しい面がある。横浜駅に限れば、残念ながら決して「美しい」とも「見やすい」とも言えない。
なぜ24ドットのものがあるかといえば、最近のものは別として、1986年ごろのPC-H98シリーズ発売による「ハイレゾ」(高解像度)のブームがあったからではないかと思われる。
旧型電光掲示板もまだまだ現役
ATOS線区では、旧型の電光掲示板も数種類が使われている。
総武線の錦糸町では、快速ホームに8つある電光掲示板のうち、新型は上り用の2つだけで、6つは旧型である。 新宿で使われている電光掲示板は、錦糸町で使われているものと同じタイプの電光掲示板に「飾り」を取り付けてある。東京の地下ホームでも同じタイプの電光掲示板が使われており、更新時期が来るまで交換されずに使われ続けるものと見られる。 |
京浜東北線では、以前から電光掲示板が設置されていた駅が多い。ATOS導入にあたって既存の電光掲示板を交換することも無く、大半の駅で今もそのまま使われている。 ただ、旧型の電光掲示板はいずれもLEDの劣化が進んでいる。特に緑色の劣化が著しく、緑と赤を同時に点灯させて表示する橙色が、まだらに見えるようになってきている。また、新型では高輝度タイプのマトリックスが使われているが、旧型では低輝度タイプのものもある。 |
電光掲示板の移り変わり
現在一般的な型の電光掲示板が登場する直前の型といえる電光掲示板もある。京浜東北線の一部の駅、田町−田端間の山手線ホームでは、方面表記のデザインはほぼ最新型と同じでありながら、本体の上下が丸みを帯びているタイプが使われている。 品川では、本体は最新型でありながら、方面表記が異なるタイプの電光掲示板が設置されている。路線名の表記がないのは、今では考えられないことである。 |