
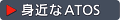
→ 運行管理の変遷
今後の課題や参考文献はフォーラムで紹介しています。投稿も受け付けています。
→ 「連動」を含む発言(記事)の一覧(新着順)
→ キーワード・ナビ「軌道回路」
→ 【訂正】
このフォーラムについて 利用規約
ATOSについてより深く理解するには、列車運行管理の役割やシステムの変遷にも目を向けることが欠かせません。連動装置、CTCから、PRC、TTC、ATOS、COSMOSに至る列車運行管理の変遷を、わかりやすくまとめてみました。
手動操作から機械制御・集中制御へ
鉄道が登場した当初、ポイントや信号機を動かしていたのは人間だった。しかし、運転本数が増えると制御が複雑になった。同時に複数のポイントや信号機を間違いなく動かさないと、列車は正しい進路に進めない。そこで登場したのが「連動装置」である。
連動装置はあらかじめ組み立てられた論理回路により、ポイントと信号機を適切に切り替える。係員が操作する上では、一定の切り替えパターンを「進路」(上図では青線で示した)として扱うため、誤った切り替えを行なう心配がない。
連動装置は各駅に置かれ、係員が操作していた。しかし、これでは駅ごとに連動装置を操作する係員を配置する必要がある上、路線全体を把握して管理することも難しい。そこで、連動装置を一箇所から遠隔操作することが考えられた。そのために作られたのがCTCである。
CTCは駅装置と中央装置とで構成され、各駅の連動装置にCTCの駅装置を追加、中央装置と接続する。中央装置には列車位置の表示盤が設けられ、路線全体を把握した効率的な運行管理が可能になった。
ちなみに、多くの人が「運行管理システム」と聞いて連想するのは、壁一面の大きな表示盤がついた、このCTCであろう。見栄えが良いためか、必ずしも表示盤にする必要がない最新のシステムでも、わざわざCTCのような表示盤が設けられることがある。
コンピュータによる自動制御へ
CTCにより操作場所が一箇所にはなったが、人間が操作していることに変わりはない。運行形態が複雑化するにつれ、人間の手では追いつかなくなってきた。決められたダイヤに従って、自動的に操作できれば…と開発されたのが、PRCである。
PRCでは、あらかじめ設定した手順(プログラム)通りに、コンピュータが自動でポイントを切り替える。
PRCの登場により、鉄道の運行管理は格段に効率化した。とはいえ、それはあくまで列車がダイヤ通りに動いている間のみの話である。いったんダイヤが乱れるとPRCは使えなくなってしまう。
運行管理システムの登場
そこで新たに開発されたのが、TTC・PTCなどの運行管理システムである。これらのシステムでは、指令員が列車の動きを監視しながら簡単な操作でダイヤを変更でき、変更したダイヤに基づいて自動制御を続けることができるようになった。ダイヤが乱れても対応できるシステムに進化したのである。
しかし、TTCのような運行管理システムの導入が進んだのは、大手私鉄などの一部に限られた。東京圏のJR線では複数の路線が複雑に絡み合い、いずれの路線でも列車が高密度に運行されている。システムは大規模なものにならざるを得ず、しかもリアルタイム処理が必要なため、とてつもない性能を要求される。東京圏のJR線に対応する運行管理システムの登場には、コンピュータの高性能化を待つ必要があった。
自律分散型システムで超高密度線区にも対応
1993年、高性能化が著しい汎用機器を活用し、自律分散アーキテクチャを取り入れ、ようやく実現したのがATOSである。
自律分散型システムのメリットは、システムの一部が停止しても、システム全体は停止しないということである。これにより、超大規模でありながら信頼性の高い運行管理システムが構築できるようになった。
ATOSは、10年以上もの時間をかけて段階的に構築されている。また、初期に導入された部分では早くも更新が始まっている。システム全体としては常に新しい状態を保つことができ、まるで生き物のようなシステムである。
待たれる総合システム化
ATOSにもまだ足りない部分がある。それは、車両や人員、電力などの管理、車両基地での構内作業には対応していないことである。新幹線では、これらを総合的に管理できるCOSMOSが実用化されている。在来線での実用化が待たれるところである。
※このページは、鉄道各社の広報資料や信号機器メーカーの技術誌、鉄道工学・情報システム学のテキスト等を参考にして作成しました。
関連ページ
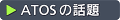
・ フォーラム
→ 【北九州モノレール】日立製作所「自律分散ループ伝送システム」を採用した「北九州高速鉄道小倉線運輸管理システム」(1985年1月)
→ 大同信号「総武快速TID装置(SN95)」(2004年2月)
→ 成田線・成田空港高速鉄道線(1991年3月)
→ 伊豆箱根鉄道駿豆線(1924年)・伊豆急行線(1961年)
→ 伊豆箱根鉄道駿豆線でCTC導入(1985年11月)
→ 直通運転に欠かせないATSとCTC:進路制御と列車番号の関係を探る
→ 「オペラン-D」(1968年)
→ 「コムトラックph-2」(1972〜1975年)に見る「旅客案内の機械化・自動化」
→ 【東北新幹線・青函トンネル】日立製作所「SAINT(Shinkansen ATC and INTerlocking system)」(2007年11月)
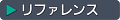
・ 鉄道システム
|