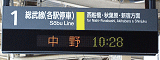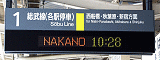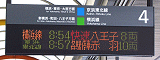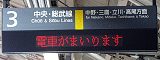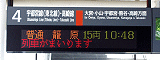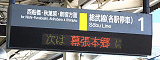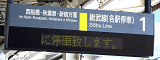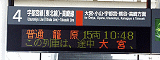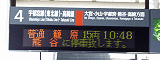| 2005/7/15(金) 更新 |
最もシンプルなものでは、「行き先」「発車時刻」の2項目が表示される。必要に応じて、「種別」「両数」「列車名」「号数」「始発」「路線名」などの詳しい情報が加わっていく。 「行き先」などの表示は、かな漢字とローマ字で交互に表示される。かな漢字表示が10秒、ローマ字表示が5秒で、かな漢字のほうが長くなっている。 「行き先」と「列車名」が交互に表示される駅では、「行き先」と「列車名」のかな漢字表示が5秒ずつ、ローマ字表示が2.5秒ずつになっている。このような表示方法は、総武線(快速)の駅で最初に使われ始めた。 |
接近/通過警告表示(赤字点滅)
電車がホームに接近する時、放送が流れ始めると同時に電光掲示板にも警告表示が点滅する。
基本は「電車がまいります」だが、電車と列車の別がある。いわゆる「E電」(近距離電車)が「電車」、「M電」(中距離電車)や特急、臨時、回送、貨物列車が「列車」と表示される。ちなみに、線区別中央装置からダイヤの情報が送られてこない場合は、列車検知器が反応し次第、「列車がまいります」と点滅するようになっているらしい。この現象は、ダイヤが乱れたときや、先行導入の駅で見ることができる。 |
電車がホームを通過する場合は「○○が通過します」と出る。通過の場合のみ、電車が通過し終えるまでずっと点滅したままになる。また、2行タイプの場合は、下の行に「○○が通過します」と点滅している間、上の行が非表示になる。 |
|
停車駅案内(スクロール)
「○○がまいります」の点滅が終わった後(およそ、接近放送が流れ終わった後)、その時到着する電車の停車駅を知らせるスクロール表示が流れる。
2行タイプの場合は、下の行にスクロールする。スクロールしている間も、上の行には電車の案内が表示されている。始発駅では、その電光掲示板で案内している先発電車の発車3分前ごろから発車までの間に数回、スクロールする。
多くの駅では「(←)次は□□□□□に停車致します。」という表示で、全角5文字分のところに駅名が入る。恐らく、この表示が標準の設定なのであろうが、一部の駅では「(←)次は○○に停車します」と縮めていたりする。 駅によっては、標準設定のスクロールが流れた数秒後に、駅独自のスクロールが流れたりもする。あるいは、標準設定のスクロールは接近放送の直後だけ流れるが、駅独自のスクロールは一定間隔で常に流れている、という駅もある。 |
特急や快速など、通過する駅のある電車では、終点までの複数の停車駅が案内される。この際、スクロール表示が極端に長くならないよう、12駅が基準になっている。
終点までの停車駅が12駅以内であれば、「(←)この列車は、途中□□□□□、(…)、□□□□□に停車致します。」と表示される。 一方、終点までの停車駅が12駅を超える場合は、「(←)この列車は、□□□□□、(…)、□□□□□の順に停車致します。」と表示される。 |
停車駅スクロールは、「内回り」「外回り」がわかりにくい山手線、各駅停車と快速が同じホームに停車する京浜東北線、行き先によって別方向に向かう宇都宮線・高崎線では、特に重要な役割を果たしている。