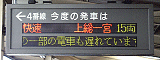| 2004/11/7(日) 更新 |
各駅の進路制御装置や旅客案内装置が使用開始になったことは、電光掲示板や自動放送で一目瞭然であるので問題ないだろう。気になるのは、どの駅が、いつから使用開始になるのか、ということではないだろうか。 |
 (川崎駅、2001/10 撮影) |
東海道線の戸塚、国府津、大船、常磐線の我孫子では、いずれも線区中央装置の使用開始より先に、駅装置が使用開始になった。これらの駅は連動駅(構内にポイントのある駅)の中でも比較的ポイントの数が多かったり、線区をまたがるイレギュラーなポイントがあったりする駅である。
つまり、ここでも電子連動装置がATOSの要であることが影響してくるわけである。連動駅、特に連動駅の中でも複雑な駅の方が先に使用開始になることが多い。むしろ、進路制御をATOSと連動させる作業が進められるのと同時に旅客案内装置も使用開始になる、というのが実情のようだ。
線区ごとの中央装置が稼動するには、各駅の進路制御装置が自律的に稼動していることが前提となる。あえて旅客案内装置だけに着目すると、連動駅では線区中央装置の稼動を待たずに旅客案内装置が使用開始になることになる。このため、連動駅では一定の期間、旅客案内装置がスタンドアローン(オフライン)で稼動することになる。このことは、電光掲示板に異常時の運行情報などが一切流れないことから確認できる。
なお、総武線(快速)では線区中央装置の使用開始よりかなり早い時期に駅装置が使用開始になった。総武線(各駅停車)と並行し、連動駅では一体的に電子連動化されたためではないかと思われる。また、改札口への電光掲示板設置も行われたことから、利用客の混乱を避けるために前倒しされた可能性もある。 |
 (錦糸町駅、2000/5 撮影) |
また、山手貨物線・埼京線の大崎−十条間では、線区中央装置の本格的な稼動を待たずに各駅でATOSの駅装置が整備された。湘南新宿ラインの増発に対応するための暫定的な使用開始ではないかと見られる。
線区中央装置(ホスト)の使用開始
線区ごとの中央装置(ホスト)が使用開始になると、一般に「ATOSの使用開始」と呼ばれることになる。新聞記事やプレスリリース、技術誌などで紹介される「導入日」も、線区中央装置の使用開始日を指す。
線区中央装置が使用開始になると、運行情報など指令室から送られてくるメッセージが電光掲示板に表示されるようになる。また、ダイヤが乱れたときには、電車の遅れ具合が案内に反映される。 |
出発時機表示器は、普段は消灯しているため使用開始がいつなのかはわかりにくいが、仕組み上、線区中央装置の使用開始と同時に使用開始になっているものと考えられる。なお、実際には、それ以前に白い×字のテープが剥がされていることが多い。
総武線(快速)、横須賀線では、電光掲示板などの挙動から、2000年9月30日に線区中央装置が使用開始になったものと見られる。写真は、その2日後に早くも出発時機表示器が使用されている様子である。総武線(各駅停車)では、1999年5月29日に初めて出発時機表示器の使用が目撃されている。 |
 (船橋駅、2000/10/2 撮影) |
一ヶ月以内には全駅で使用開始
非連動駅(構内にポイントのない駅)での旅客案内装置などの使用開始は、線区中央装置の使用開始後、数週間から遅くとも一ヶ月以内に完了している。