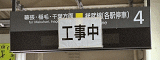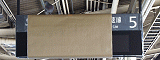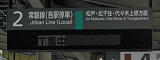| 2004/11/7(日) 更新 |
運転本数の多い区間を中心に、各駅のホームや改札口などに電光掲示板が設置される。 既に設置されている駅でも、設置されている電光掲示板が古い場合や、番線ごとに設置されていない場合など、一定の要件を満たさない場合は新しいものに交換されることがある。 例えば、大船駅では電光掲示板が既設だったが、写真のようにホームに一つという設置形態だったため、新しく番線ごとに設置された。余談だが、ここで撤去された電光掲示板はリニューアルの上、東戸塚駅の改札口に転用されている。 |
 (新松戸駅、2004/1 撮影)  (大船駅、2000/5 撮影) |
設置後はしばらく「工事中」
ほとんどの駅で、まずホーム上、階段付近の案内サイン類が撤去(移動)された後、新たに電光掲示板が設置される。各線区での実例は「導入済み線区」を参照していただきたい。 設置後は「工事中」という貼り紙が貼られ、しばらくの間は動きがない。梱包材で包まれたままにされる場合もある。 初期の導入線区では、電光掲示板の設置から使用開始までに約半年かかっていたが、最近の線区では数ヶ月程度だったこともある。これは線区の駅の数にもよるものと見られる。 |
設置形態の変化
電光掲示板には発車時刻等を案内するだけでなく、異常時に運行情報を伝えるという大きな役目もある。そのため、初期の導入線区ではホーム上だけに設置されるのが基本だったが、後から改札口への設置が進められた。概ね東海道線以降では、当然のように改札口にも電光掲示板が設置されている。
ただし、最近になってPHSデータ通信網を活用した運行情報専用の小型電光掲示板も開発されており、今後の導入線区でどのような設置形態が取られるかは未知数である。
→ 試験
関連ページ
・ トピックス
→ ATOS導入後の千葉駅緩行ホーム
→ 写真で見る稲毛駅電光掲示板設置前後
→ 総武線地下区間のATOS/ATS-P関連機器
→ 「工事中」を知らせる工夫〜電光掲示板編
・ フォーラム
→ 「ホーム系」と「改札系」の違いと軌道回路
→ 千葉駅に見る「ホーム系」と「改札系」
→ 直通運転に欠かせないATSとCTC:進路制御と列車番号の関係を探る
→ ノイズの多い駅ホームで「512色中8色」を実現した「パレットマルチカラー発車標」