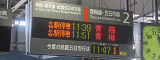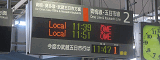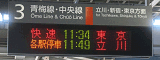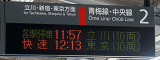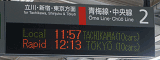| 2014/9/16(火) 新設 |
通告伝達システムでは、在線位置にかかわらずいつでも伝達が可能で、乗務員による受領確認が行なえるなど、出発時機表示器に対する優位性がある。これは、青梅線・五日市線とともにATOS導入の対象となった横浜線、京葉線についてもいえることである。 |
 (西立川駅、2014/7 撮影) |
出発時機表示器の設置によって、かえって柔軟性が損なわれることがあっては本末転倒である。現に、京浜東北・根岸線に直通する横浜線の電車や、武蔵野線と中央線(快速)を直通する「むさしの号」は、直通先の線区では対応する位置に出発時機表示器がなく、出発時機表示器の対象外となる特急列車や臨時列車などと同等の取り扱いとなっており、異常時には直通が中止される。車両側の設備の活用による、すべての列車をきめ細かく管理できる環境の実現が期待される。今後、最初にATOSが導入される線区での動向が注目される。
拝島:電光掲示板がPRCに連動、
五日市線の案内に工夫
拝島から発車する五日市線の下り列車は、立川方面からの直通列車と、拝島で折り返す列車とで、のりばが異なる。拝島の2番線には、武蔵五日市行き列車の発車時刻とのりばを案内する全角4文字分のLED表示面が追加された電光掲示板が設置されている〔写真〕。 |
 (拝島駅、2014/7 撮影) |
3番線には通常の2行タイプの電光掲示板が設置されているが、最下部の掲出高さが揃えられているため、同種の情報が水平に並ばなくなっている。また、多くの駅では2台の電光掲示板を左右に配置し、中央に時計を設置するのが一般的であるが、2番線の電光掲示板より線路側に時計が設置されている。 拝島の電光掲示板はいずれも、ATOS導入直前の津田沼、品川などと同じ書体での表示となっている。 |
立川−西立川間に「青梅短絡線」
中央線との直通、線区別ホスト共用でスムーズに
青梅線の立川−西立川間では、複線の線路に加え、単線の「青梅短絡線」が設けられている〔上動画(30秒)〕。青梅短絡線は、立川−日野間の中央線と立体交差になっており、中央線および南武線から青梅線へ直通する下り列車〔下動画(30秒)〕、および、青梅線から南武線へ直通する上り列車が短絡線を経由して運転される。
しかし、西立川では、短絡線から入線する下り列車の接近を知らせる自動放送が、列車のホームへの進入の直前まで流れないという問題がある。青梅短絡線の進路制御は中央線側で行なわれているとみられ、西立川の駅装置では、下り列車が西立川の場内信号機に進入するまで、在線を検知できないのではないかと考えられる。青梅短絡線は単線自動閉そく式で、単線区間の途中にも閉そく信号機が設けられていることから、中央線と同一の線区別ホストを使用する形での青梅線へのATOS導入により、この問題が解消できるとみられる。 |
(西立川駅、2014/7 撮影) |
一方、青梅線から中央線へ直通する上り列車について、立川での進路制御には、青梅線側のPRCが把握する上り列車の在線位置が、中央線側のATOSに伝達される必要がある。
現状では、青梅線から中央線へ直通する上り列車で、西立川で数分停車する列車がある。情報の伝達に何らかの人的対応を要しているとは考えにくいが、停車時間の長さがシステム上の都合によるものである可能性がある。 |
さらに、これはシステム以前の制約であるが、立川の手前で分岐器による35km/hの速度制限を受けるほか、3番線のホーム中間に追加の場内信号機がなく、先行列車がわずかに遅れるだけでも場内信号機の手前で一旦停止することになるため、西立川での停車時間の長さも含め、立川までの所要時間が長くなる列車が生じている。中央線でのATOS更新および青梅線へのATOS導入により、両線の列車の在線位置がシームレスに把握できるようになるとともに、西立川および日野の双方で上り列車に適切な延発を指示することができるようになれば、この区間での運行が多少はスムーズになると期待される。とはいえ、システムや運用での改善には限界があり、抜本的には線路や信号設備の改良が待たれる。
青梅線の立川−東中神間では連続立体交差化が予定されている(※3)。この工事が始まるまで、この区間で線路や信号設備が改良されることは期待できない。西立川では、ホーム上屋の延伸も行なわれないままである〔写真〕。 |
 (西立川駅、2014/7 撮影) |
※3 2004年6月に東京都都市整備局が公表した「踏切対策基本方針」で、「鉄道立体化の検討対象区間」として、南武線の矢川−立川間、青梅線の立川−東中神間が挙げられている。立川の配線が決定しない限り、事業化されないとみられる。立川市の構想では、複線の青梅線および単線の青梅短絡線の計3線の「高架化」(意図としては「踏切の除却」であり、線路構造は未定とみられる)を目指すとされている。また、中央線の三鷹−立川間の複々線化が事業化されているが、未着工である。
八高線でPRC導入済み
長期的にはATOSへ切り換えか
八高線は、1996年3月に八王子−高麗川間が電化され、現在、川越線(川越−高麗川間)と直通運転を行なっている。
八高線では、八王子−高麗川間の全駅で列車の行き違いが可能であるが、直通している川越線内では、笠幡および西川越で行き違いができない。このため、全駅で行き違いを行なう「ネットダイヤ」にはなっておらず、八高線側では設備上の輸送能力を活かしきれていない状態である。
北八王子では、改札口のみに電光掲示板が設置され、ホームには設置されていない。自動放送では、行先などの詳細な案内が行なわれない〔動画(30秒)〕。 |
(北八王子駅、2014/7 撮影) |
駅周辺に工場や宅地が広がり、乗車人員は八高線で最も多いが1万人を超えておらず、バリアフリー設備としてはエレベーターのみの設置となっている〔写真〕。日中の列車あたりの乗降客は数人であるが、乗換駅の間を乗り通す利用客は比較的多く、列車そのものは日中でも座席が半分以上埋まる状況になっている。 |
 (北八王子駅、2014/7 撮影) |
八高線のCTCも拝島に置かれ、PRCが導入済みである。川越−武蔵高萩間でATOS導入済み、拝島では青梅線の駅としてATOSへの切り換えが予定される中、八王子−高麗川間(拝島を除く)が取り残される。ATOSの導入には、現地のCTCセンターに置かれた指令を東京に一元化する目的もあることから、拝島に八高線の指令だけを残すことは考えにくい。
青梅線・五日市線へのATOS導入では、独立した線区別ホストが新設されず、中央線と同一の線区別ホストが使用される見通しであることから、八高線についても、仮にPRCからATOSへ切り換える場合、中央線または川越線と同一の線区別ホストを使用する措置が取られると考えられる。
長期的には、高麗川や、八王子での貨物関連を含む配線の整理、川越線での行き違い設備の増設、箱根ケ崎電車区(仮称)の設置、青梅線および南武線の連続立体交差化などと合わせて取り組まれるものとみられる。すなわち、連動装置の改修が必要とならない限り、旅客案内装置やダイヤに大きな変更が加えられることは原則ないといえる。
なお、八王子−高麗川間では、2001年度にATS-Pが導入されている。ATS-Pの導入時期として遅いものではなく、十分な投資が適切な時期に、八高線でも行なわれてきていることを示している。
関連ページ
・ 導入済み線区
→ 中央線(快速)・中央本線
→ 埼京・川越線
→ 南武線
・ ニュース
→ 【ATOS拡大】 青梅線・五日市線、横浜線、京葉線に導入へ
・ トピックス
→ フォントでわかる電光掲示板のATOS連動/非連動
・ フォーラム
→ 「運行管理システムの変更」に着手か(2017年2月)
→ 青梅線・南武線と交差する都市計画道路(2015年12月)
→ 【中央線(快速)】2020年度にグリーン車増結、12両化へ(2015年2月)
→ 【八高線】特開平5−58302「仮想踏切」(1993年3月)