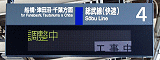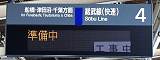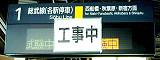| 2004/11/7(日) 更新 |
この時期になると、日中に電光掲示板を開けて何やら確認している様子が見られることがある。すぐにでも使用開始になるのではないかと期待してしまうところだが、そうも行かないようである。 |
 (新小岩駅、2000/5 撮影) |
電光掲示板の試験でも、電光掲示板そのものの試験(調整・確認)、電光掲示板に情報を表示するための制御装置の試験、その制御装置をATOSと接続する試験と、複数のステップがある。 |
 (市川駅、2000/5 撮影) |
電光掲示板と制御装置が動くようになると、「調整中」という表示が見られるようになる。詳しくは「ATOS最新情報/トピックス」等を参照していただきたいが、この時点では電光掲示板の制御装置はATOSと連動していない。 駅に設置されたATOS装置と連動すると「準備中」と表示され、電車の接近時に「列車がまいります」と点滅したりするようになる。 なお、「列車がまいります」の点滅表示は、ATOS導入前に整備される単純な自動放送や、従来からの「電車が/きます」というLED式表示器や「こんどの電車は○○を出ました」という行灯式表示器と同様の仕組みで表示される模様だ。この時点では特別にATOS特有の動作をしているわけではないようである。 |
後述する線区ごとの中央装置との接続試験が始まると、運行情報が流れることがある。ここまでくれば、ATOSならではの高度な旅客案内を実現する準備が大方整った状態と見ることができる。
自動放送のテストでは、一時的にATOS連動の放送に切り替えられたりする。その場に居合わせればテスト中であることが明確だが、すぐに元の自動放送に戻ってしまうので、テストが行われたことを知るのは難しい。
その他の試験
ここまでは利用客の目に触れるところで行われる試験が多いが、見えないところでも様々な試験が行われているであろうことは容易に想像できる。
電子連動装置は、導入後すぐに使用されるものと見られるが、ATOSと接続してPRCとして運用するためには何らかの試験が行われる可能性がある。また、線区ごとの中央装置については、各駅の装置や他線区の装置、輸送総合システムなど他のシステムとのデータの送受信などが試験されるものと思われる。
保守作業時に作業員が自ら線路閉鎖をかけられる携帯端末や、駅員に運行情報を知らせる携帯端末、指令室の輸送指令卓、各駅では在線モニタなど、人間系とシステムのインターフェースについては、単に機器の試験だけでなく、操作方法の研修なども必要になるものと思われる。
関連ページ
・ トピックス
→ フォントでわかる電光掲示板のATOS連動/非連動